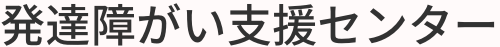宿題ができない・忘れ物が多い発達障害の子に、親ができること
〜「やらせる」より「仕組み」でラクになる関わり方〜
こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
「また宿題を忘れたの?」
「どうして毎回、忘れ物をするの?」
そんなふうに言いたくなる日、ありますよね。
でも実は、発達障害の子どもたちが「宿題」や「持ち物の準備」が苦手なのには、それなりの理由があります。
「やる気がない」わけじゃない
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、集中力が途切れやすく、「やることを覚えておく」ことが苦手なことがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、こだわりが強く、頭の中で予定を立てても柔軟に切り替えるのが難しいことがあります。
LD(学習障害)の子どもは、読み書きや手順を整理するのに時間がかかることがあります。
つまり「やりたくない」ではなく、「どうやって取りかかればいいか」がわからないのです。
大人が手助けをすれば、「やる気スイッチ」が入りやすくなる子もたくさんいます。
「入口支援」でハードルを下げる
ポイントは、“宿題をやる”ことではなく、“宿題に取りかかる入口”をつくること。
たとえば、
「学校から帰ったら、ランドセルから宿題を出して机の上に置く」
この一歩だけでOKにしてみましょう。
もし、すぐにできないようなら、
・宿題を入れる「ボックス」を用意する
・帰宅したら「とりあえずここに入れる」だけでOK
という形でも構いません。
目につく場所にあるだけで、「あ、宿題あったな」と思い出しやすくなります。
最初から全部やらせようとせず、“できた部分”を認めてあげることが大切です。
「忘れ物」を防ぐのは「一緒に準備」
「自分でやらせなきゃ」と思うほど、親子でぶつかりがちになります。
でも、忘れ物を減らすコツは、「一緒にやる」ことなんです。
明日の時間割を見ながら、「これは必要?」「体操服は洗ってある?」と、会話しながら準備します。
慣れてきたら、リストを一緒に作って、「これを見ながら自分でできるね」と段階的に任せていけばOK。
もし可能なら、教科書を学校に置いておけるよう先生に相談してみるのもいいかもしれません。
“忘れ物を生まない環境”を整えるのも立派なサポートです。
「できない」を叱るより、「仕組み」で支える
発達障害の子どもにとって、「忘れる」「手順がわからない」は、努力不足ではなく脳の特性によるものです。
叱っても改善は難しく、むしろ自己肯定感を下げてしまうこともあります。
だからこそ、
「どうしたらスムーズに動けるか?」を一緒に考える視点が大切です。
“声かけ”よりも“仕組みづくり”。
“注意”よりも“一緒に行動”。
これが、親も子もラクになれる関わり方です。
おわりに
宿題や忘れ物の問題は、「子どもの努力」ではなく「環境の工夫」で変わります。
最初の一歩は、「やらせる」より「一緒にやってみる」こと。
あなたの少しのサポートが、
子どもの「できた!」を増やし、
「自分はできる」という自信を育てていきます。