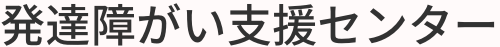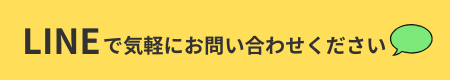〜心と体を整える“ちょっとしたコツ”〜
こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
発達障害がある方は、感覚が敏感だったり、逆に鈍かったりすることで、食事に関する悩みを抱えやすいと言われています。
たとえば、偏食が激しい、特定の食感が苦手、味やにおいに強く反応してしまうなど…。
それは「わがまま」ではなく、脳や感覚の特性によるもの。
だからこそ、自分を責める必要はありません。
でも、食生活が乱れると心や体にも影響が出やすく、気分の落ち込みや集中力の低下、体調不良につながることもあります。
ここでは、発達障害のある人が無理なくできる食生活の整え方を、やさしくお伝えします。
① 「完璧な食事」じゃなくていい。まずは“抜けを補う”意識を
発達障害のある人は、食べられるものに偏りが出やすく、ビタミンやミネラルが不足しがちです。
特に不足しやすい栄養素は、以下のようなもの:
- 鉄分:疲れやすい、イライラする
- マグネシウム:神経の興奮をしずめるミネラル。不安感や睡眠トラブルに関係
- 亜鉛:集中力や味覚に関係
- ビタミンB群:脳や神経の働きをサポート
偏食があると、どうしてもこれらの栄養素が足りなくなることがあります。
でも大丈夫。“できる範囲で補う”だけでも違います。
たとえば…
- ごはんに雑穀を混ぜて、ミネラルをアップ
- おやつにゆで卵やチーズをプラスして、たんぱく質を補う
- 食べられる野菜を、スープやジュースで摂る
そんなちょっとした工夫が、自分の心と体を守ることにつながります。
② 「食感」「におい」など、苦手は無理せずスルー
「野菜の青臭さが苦手」「ドロっとした食感がどうしてもダメ」
そんな“感覚の敏感さ”がある方も多いと思います。
無理にがんばって食べようとすると、食事がストレスになってしまいますよね。
だから、苦手を避けても大丈夫。代わりに同じ栄養が摂れるものを探しましょう。
- トマトが苦手 → パプリカやにんじんジュースで代用
- 牛乳が苦手 → ヨーグルトやチーズでカルシウムを補う
- 緑の野菜が苦手 → スムージーや青汁もひとつの手段
「これはOK」「これはNG」と、自分の“感覚マップ”を作っておくと、買い物や献立が楽になります。
③ 甘いもの・刺激物に要注意!心が不安定なときほど控えめに
ストレスがたまると、つい甘いお菓子や炭酸飲料に手が伸びてしまうことがあります。
でも、砂糖やカフェインを取りすぎると、気分の波が大きくなったり、イライラや不安を引き起こすことも。
もちろん、甘いものが“癒し”になることもあるので、完全にやめる必要はありません。
大切なのは「量」と「タイミング」です。
- 甘いものは、空腹時や寝る前を避けて、午後のおやつタイムに
- ジュースは1日1杯まで、できれば水やお茶に置きかえる
- 甘いものが欲しいときは、ドライフルーツやバナナもおすすめ
「どうしてもやめられない」ではなく、**「付き合い方を変える」**ことが大切です。
④ 水分不足も大敵!頭のモヤモヤ、実は「脱水」かも
意外と見落とされがちなのが、「水分」です。
気分が落ち込んだり、集中できないとき、実は軽い脱水状態のこともあります。
とくに、カフェイン飲料ばかり飲んでいると、利尿作用で体内の水分が減ってしまいます。
できれば、
- こまめに常温の水を飲む
- 朝起きたらまず一杯の水
- カフェインの摂りすぎに注意
という習慣を意識してみてください。
最後に:あなたの“体”は、あなたの味方
食生活を少し意識するだけで、心のざわざわや体の不調が和らぐことがあります。
でも、いちばん大切なのは、**「自分を責めないこと」**です。
完璧な食事じゃなくてもいい。
1日1つでも、「ちょっと意識してみること」から始めてみてください。
心と体は、ちゃんと応えてくれます。
あなたの“今日を生きる力”を、食べものがそっと支えてくれる。
そんな日常を、少しずつ作っていきましょう。