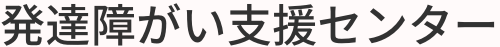水遊びが子どもにくれるやさしい時間と、忘れてはいけない「水辺の安全」
こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
「うちの子、水が大好きなんです」
そんな声を聞くことがよくあります。
お風呂でバシャバシャ遊んだり、洗面所でずっと手を濡らしていたり…。
特に自閉症スペクトラム症(ASD)をもつ子どもたちは、水の感触や音、光の反射などに安心感や心地よさを感じることが多く、水遊びは“癒しの時間”にもなります。
けれどその一方で、私たち大人が知っておかなければならない、大切なこともあります。
ASDの子どもにとって、水辺の事故リスクは非常に高いという事実です。
自閉症スペクトラム症(ASD)の子どもはなぜ水辺の事故が多いのか?
アメリカの研究では、ASD児の死亡原因の約46%が溺死というデータが出ています。
これは一般の子どもたちに比べて、はるかに高い数字です。
日本でもプール、川、ため池などでの水の事故が後を絶ちません。
ASDの子は、感覚の過敏や鈍さがあり、「冷たい」「深い」「危ない」といった危険を察知しにくい場合もあります。
また、水への強いこだわりから、危険な場所でも水に近づいてしまうこともあります。
ASD(自閉症スペクトラム症)の子どもたちが水辺の事故に遭いやすいのは、いくつかの特有の特性や行動パターンが関係しています。以下は、その主な理由です。
① 危険を察知しにくい感覚特性
ASDの子どもは、感覚がとても敏感だったり、逆に鈍かったりする「感覚の偏り」があることが多いです。
たとえば…
- 冷たい水や深さを感じにくい(=危険を察知できない)
- 水に顔がついても怖がらず、ずっと潜り続けてしまう
- 水の音や光に夢中になり、自分の置かれた状況に気づきにくい
こういった感覚の違いにより、水の中で“危ない”という直感が働きにくく、事故につながるリスクが高まるのです。
② 「水へのこだわり」が強く、制止がきかないことも
ASDの子どもは特定のものに強く惹かれる「こだわり傾向」があります。
その対象が「水」である場合、水を見かけると飛び込んでしまったり、川や池に吸い寄せられるように近づいてしまうことがあります。
しかも、一度興奮状態に入ると、大人の呼びかけが届きにくくなることも少なくありません。
③ 行動の予測が難しい・急な動きがある
ASDの子どもは、その場の状況や危険性を判断するのが苦手なことがあります。
突然走り出す、いきなり水に飛び込むといった“予測しにくい動き”が起きることも。
そのため、たとえ安全に見える場所でも、大人が目を離したほんの数秒で事故につながるケースがあるのです。
④ 方向感覚・空間認知の困難さ
水の中では、自分の身体の位置や動きの感覚(ボディイメージ)をつかむのが難しくなることがあります。
ASDの子どもは、もともと「バランス感覚」や「空間の広がり」を把握するのが苦手なこともあり、
ふいに足を取られたり、浮力のコントロールができずパニックになってしまうこともあります。
⑤ 保護者が「まさかこんなことで」と油断しやすい
ASDの子は普段、過敏やこだわりが強く、「水が苦手」に見えることがあります。
そのため、「この子は水に近づかないだろう」と思ってしまい、危険な場所でも気を抜いてしまうことがあるのです。
しかし、突然好奇心に火がついて水に手を伸ばすことも。
子どもの反応や行動が日によって変わりやすいASDの特性が、事故の“意外性”を高めているとも言えます。
それでも、水遊びにはすばらしい効果がある
水遊びには、ASDの子どもたちにとって嬉しい効果がたくさんあります。
感覚のバランスを整える
- 水は視覚、触覚、聴覚を同時に刺激し、感覚統合の練習になります。
- さらさら、ぬるぬる、ひんやり…さまざまな感触が刺激となり、五感を育ててくれます。
心を落ち着ける
- 流れる水の音や、繰り返しの動作は心をリラックスさせる作用があります。
- 「コップから水を移す」などのシンプルな遊びでも、安心感や集中力アップにつながります。
コミュニケーションの土台になる
- バケツリレーや順番遊びなどを通して、交代・お願い・待つなどの社会的スキルが自然と育ちます。
楽しい水遊びを“安全に”楽しむためにできること
水遊びは確かに楽しく、発達のサポートにもなりますが、安全対策ができてこそその価値が活きます。
🔸 必ず大人が見守ること
どんなに浅い水でも、たった5cmの水でも溺れる危険性があります。
顔をつけるのが好きな子、じっと水を見つめる子など、予想外の行動が起こることも。
🔸 水温と水量に配慮する
- 夏でも冷たすぎる水は体への負担に。
- お風呂の水は膝下まで。残り湯があるときは必ずフタを。
🔸 おもちゃや遊び道具の安全性をチェック
- 誤飲の心配がない大きさか?
- 壊れにくく、ケガの心配がないか?
- カビやぬめりがないか?
🔸 感覚に合った遊びからスタート
- 水が苦手な子には、霧吹きやスポンジを使って慣らすところから。
- 顔に水がかかるのを嫌がる場合は、ゴーグルや帽子を活用。
まとめ:水遊びは成長をサポートする“宝箱”。でも、安全がカギ!
ASDの子どもたちにとって、水遊びはただの遊びではありません。
安心できるリズム、感覚の刺激、自分でコントロールできる楽しさ——
すべてが、子どもにとっての「成長の入り口」になります。
でもその反面、水辺には思わぬ危険がひそんでいるのも事実。
だからこそ、「遊び」と「安全」をセットで考えることがとても大切です。
子どもの「水が好き!」という気持ちを大切にしながら、
大人が安心・安全をしっかりサポートしてあげることで、
水遊びは親子にとっても、かけがえのない時間になるはずです。