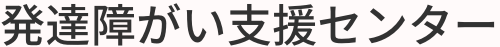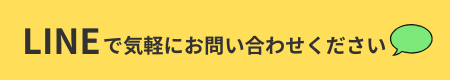偏食の子に大切なのは「食べさせること」より「わかってあげること」
こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
「野菜を食べない」「白いごはんしか食べない」「同じものばかり欲しがる」
そんなお子さんの食事に、つい困ってしまうことはありませんか?
「どうして食べてくれないの?」「好き嫌いが多すぎる…」と悩んでしまう気持ち、よくわかります。
でも、実は“偏食”には、性格やわがままではなく「感覚の違い」が関係していることがあるのです。
「嫌い」じゃなくて「つらい」と感じていることも
発達障害があるお子さんの中には、感覚がとても敏感な子がいます。
たとえば——
- 食べ物のざらざら・ぬるぬるした食感が苦手
- 噛んだときの音や匂いが強く感じられてしまう
- 温かさや冷たさに敏感で、温度差に驚いてしまう
こうした刺激が、子どもにとっては大きなストレスになることがあります。
つまり「嫌いだから食べない」のではなく、
「体が受けつけないくらい不快に感じている」こともあるのです。
まずは「観察」から始めてみよう
大切なのは、「どうすれば食べるか」よりも、
「この子はどんな感覚が苦手なんだろう?」と理解しようとすることです。
たとえば、
- 温かいスープが苦手なら、冷まして出してみる
- 食感が苦手なら、細かく切ったり、ペーストにしてみる
- 色や見た目で拒否するなら、盛りつけを工夫してみる
そんな小さな工夫ひとつで、「ちょっと食べてみようかな」と思える子もいます。
「食べられない」ことを責めないで
無理に食べさせようとすると、子どもはますます“食べること”が怖くなってしまいます。
焦らず、少しずつ「安心できる環境」で食事をすることが何より大切です。
お子さんが「食べられない理由」を理解してあげることで、
親子の食卓が少しずつ笑顔に変わっていきます。
おわりに
偏食は「直すもの」ではなく、「その子の特性に合わせて寄り添うもの」。
発達の特性を知ることで、子どもへの見方がやわらぎ、
親の心もふっと軽くなることがあります。
「うちの子もそうかも」と感じたら、
一人で抱え込まずに、専門家に相談してみてくださいね。
お子さんに合った“食のペース”を一緒に見つけていきませんか。