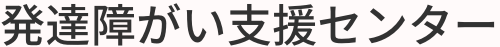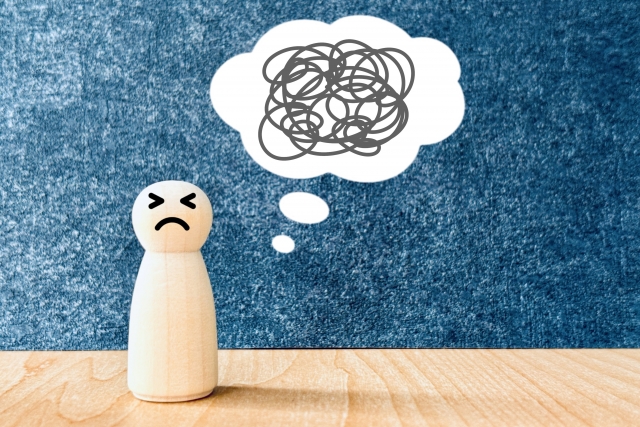
こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
発達障害のある人をサポートするとき、
目の前で起きていることだけを見て判断するのは危険かもしれません。
たとえば、
・落ち着きがない
・宿題をやらない
・話を聞いていないように見える
・マイペースで動かない
このような表に見える行動って、つい「そこを直さなきゃ」と思ってしまいますよね。
でも、
行動というのは、氷山のほんの先っぽなのです。
その下には、その人の「感じていること」「困っていること」「うまく言葉にできない理由」が、たくさん隠れています。
見えている行動だけを直そうとすると、心が傷つく
たとえば、子どもが授業中に歩き回ってしまうとします。
大人の目に映るのは 「歩く」 という行動だけ。
そこで、
「ちゃんと座りなさい!」
と行動だけを抑えつけようとすると…。
その瞬間は座るかもしれませんが、
根本の「なぜ座れないのか」は何ひとつ解決していません。
むしろ、
「自分はダメなんだ」
「怒られるからやめるだけ」
という 否定感や恐怖を心に積み重ねてしまいます。
こうなるとサポートどころか、
その人の中にある「しんどさ」を悪化させてしまうことさえあります。
大事なのは「見えないところに理由がある」という視点
「歩き回る」 という行動の裏側には、ほんとうにいろんな理由が潜んでいます。
・椅子が硬くて落ち着かない
・座っている時間が長すぎる
・注目が欲しい
・授業の内容がわからなくて不安
・お腹が空いて集中できない
・感覚過敏で教室の音がつらい
こういう 「言葉にできない困りごと」 が隠れていることがほとんどです。
だからこそ、サポートするときは
見える行動→すぐ直す
ではなく、
見えない背景→じっくり考える
この順番がとても大切なのです。
抽象的な言葉で片づけない勇気
「空気が読めない」
「こだわりが強い」
「扱いづらい」
こうしたラベルのような言葉でまとめてしまうと、
その人の本当の困りごとが見えなくなってしまいます。
大切なのは、
「どんな場面で、どんな行動が起きているのか」
を丁寧に拾い上げること。
たとえば、
「空気が読めない」
→「相手の話を聞いている途中で、自分の興味のある話題に切り替えてしまう」
こんなふうに、
具体的な行動レベルに落とし込むことで、
はじめて適切なサポートが見えてきます。
サポートの本質は「相手の内側を想像すること」
発達障害がある人への支援って、
特別な魔法を使うわけじゃありません。
必要なのはただひとつ。
目に見えない世界を想像すること。
表に見える行動だけで判断せず、
その裏にある気持ち、困りごと、安心したい心を大切にすること。
これが、相手を傷つけず、
本当の意味で力になるサポートの第一歩です。
最後に
もし、今関わっている誰かが
「なんでこんな行動をするんだろう…」
と思うことがあったら、
どうか少しだけ立ち止まって、
その奥にある「言葉にならない声」を感じ取ってみてください。
あなたのそのまなざしが、
きっと誰かの安心と自己肯定感につながります。
やさしいサポートは、
「見えないところを見る姿勢」から始まります。