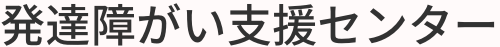「やめなさい!」が伝わらないときに知ってほしいこと
〜発達障害のある子に“わかりやすく伝える”方法〜
こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
「それ触っちゃダメ!」「大声出さないで!」
つい、こんな声かけをしてしまうことってありませんか?
危ないことを防ぎたい、周りに迷惑をかけたくない、という親の思いはとても自然なことです。
でも、発達障害(特に自閉スペクトラム傾向)のある子どもにとって、「ダメ」「しないで」と言われても、なかなか行動を変えられないことがあります。
今回は、そんなときにどう伝えればいいのかを、わかりやすくお話しします。
「ダメ!」よりも「こうしてね」を伝える
「触らないで」や「走っちゃダメ」といった否定の言葉は、一見シンプルに見えます。
けれども、子どもの脳の中では実はとても複雑な処理が行われています。
たとえば「触らないで」と言われると、
1 まず「触る」行動を思い浮かべる
2 それを「やめる」という考えに切り替える
このように、2段階の理解が必要になります。
つまり「ダメ」と言われても、「じゃあ、どうすればいいの?」 がわからないままになってしまうのです。
そこで大切なのが、「しないで」ではなく「どうするか」を伝えることです。
たとえば──
- 「触らないで」→「手はおひざにおいてね」
- 「大声出さないで」→「小さな声でお話ししようね」
- 「走らないで」→「ゆっくり歩こうね」
こう伝えることで、子どもは「してはいけないこと」ではなく、「今できること」に意識を向けやすくなります。
行動を止めるのではなく、「代わりの行動」を示してあげるイメージです。
親の安心が、子どもの理解を助ける
「どうしてわかってくれないんだろう」と感じるとき、親の方もつい焦ってしまいますよね。
でも、伝わらないのは、子どもが悪いわけではなく、伝え方の工夫がまだ見つかっていないだけです。
子どもに「できる方法」で伝えることで、親もイライラが減り、子どもも安心して行動を学んでいけます。
「言っても聞かない子」ではなく、「まだうまく伝わっていない子」なのです。
危険を学ぶのは“体験”から
子どもが「危ない」と感じられるようになるには、ただ言葉で教えるだけでは足りません。
実際に経験を通して、「あっ、こうすると危ないんだ」と体で覚えていくことが大切です。
「それはダメ!」だけで終わらせずに、
「どうすれば安全にできるか」「どうすれば楽しく過ごせるか」を一緒に考えていくと、
子どもは安心して行動の幅を広げていけます。
まとめ
発達障害のある子どもに行動をやめてもらうときのポイントは、
・ 否定ではなく、肯定の言葉で伝える
・「してほしい行動」を具体的に示す
・経験を通して理解を育てる
伝わらないときは、子どもが混乱しているサイン。
「どうすれば伝わるかな?」と、視点を変えることが、親子の関係をラクにしてくれます。
必要なのは「厳しさ」ではなく「伝え方の工夫」。
子どもの理解のペースに合わせて、少しずつ、一緒に成長していけるといいですね。