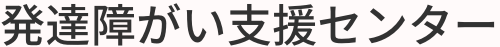発達障害のある人に必要なのは「モチベーション」よりも「システム」
こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
「よし、やるぞ!」と気合を入れても、続かない。
「今日は頑張る!」と決意しても、三日坊主で終わってしまう…。
発達障害がある方の多くが、そんな経験をしているのではないでしょうか。
社会に適応するために「モチベーション」や「気合い」だけに頼ろうとしても、それは簡単なことではなく、長続きしません。
なぜなら、私たちの脳は「やる気」や「ご褒美」だけではうまく動かない仕組みを持っているからです。
モチベーションに頼る危うさ
発達障害がある人にとって、「やる気が出ない」ことは珍しくありません。
それなのに「やる気を出せばできるはず」と自分を責めてしまうと、さらに行動できなくなってしまいます。
また、無理に“気合い”で突き進むと、一時的には成果が出ても、次第に疲れ果てて燃え尽きてしまうリスクがあります。
「緊急性」や「衝動性」でなんとか回している状態。
短期的には動けても、長期的には心身をすり減らしてしまうのです。
大切なのは「システム化」
では、どうすれば社会で安心して動けるのか。
ポイントは 「モチベーションに頼らず、仕組みに任せる」 ことです。
たとえば――
- タスクを小さく分ける(小さな一歩を踏み出せる仕組み)
- 時間を区切って動く(5分だけやる、タイマーを使う)
- 一緒に作業する仲間をつくる
- ゲーム感覚にする(ポイント制やご褒美で楽しく)
- 「とりあえず手を付けてみる」ルールをつくる
こうしたシステムを生活に組み込むことで、「やる気があるときだけ動ける」状態から、「やる気がなくても自然と動ける」状態に変えていくことができます。
まとめ
発達障害がある方が社会に適応していくためには、気合い・根性・モチベーションよりも、
システム・仕組み・習慣が大切です。
「できないのはやる気が足りないから」ではなく、
「できる仕組みがまだ整っていないから」。
そう考えることで、自分を責めずに前に進めるようになります。
自分に合ったシステムを作り、無理なく続けられる形で日常を回す工夫を考えてみるといいかもしれません。