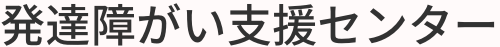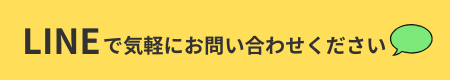こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
子どもの頃、私は運動がとても苦手でした。
跳び箱は低くても飛べない、泳げない、ボールは遠くに投げられない。
一生懸命やっているのに、まわりと同じようにできない自分が悔しくて、恥ずかしくて、苦しかった。
でも一番つらかったのは、「がんばっていない」「やる気がない」と思われること。
親も先生も、「練習すればそのうちできるようになる」と言って励ましてくれたけれど、何度やってもできなくて、だんだん自信を失っていきました。
運動が苦手な子どもの場合、単なる「運動音痴」ではなく、「DCD(発達性協調運動障害)」という発達の特性が関係していることがあります。
DCDってなに?
DCD(Developmental Coordination Disorder)は、日本語で「発達性協調運動障害」と呼ばれています。
聞きなれない名前かもしれませんが、じつは子どもの5〜8%に見られる、決して珍しくない発達の特性です。
特徴は、「知的な遅れはないのに、年齢に見合った運動がうまくできない」という点。
ただの運動不足ややる気の問題ではなく、脳の発達や運動の指令の出し方に違いがあるために、手足や目の動きがバラバラになってしまうのです。
DCDの子どもに見られる“苦手さ”
DCDの子どもには、以下のような特徴が見られることがあります。
- 走るとぎこちない動きになってしまう
- ジャンプ、スキップ、縄跳び、自転車が苦手
- 字を書くのに時間がかかる、文字が崩れる
- 箸やスプーンをうまく使えない、よく物を落とす
- 姿勢を長時間保てず、すぐにくずれてしまう
- ボールを投げたり、受け取ったりするのが苦手
これらは本人の「努力不足」ではなく、脳と体の動きの連携がうまくいかないという特性によるものなのです。
他の発達障害との関係
DCDは、単独で見られることもありますが、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)と一緒に現れるケースも多く報告されています。
特にADHDの子の約30〜50%、ASDの子の80%以上に、DCDの傾向があると言われています。
つまり、「落ち着きがない」「こだわりが強い」といった特性だけでなく、「運動のぎこちなさ」にも着目することが、子どもの本当の困りごとを理解する手がかりになるのです。
見逃されやすい「運動の困りごと」
DCDの子どもは、学習面に問題がない場合、「ちょっと不器用な子」「運動が苦手なだけ」として見過ごされがちです。
でも実際には、その苦手さによって深い劣等感を抱えたり、周囲との関わりを避けるようになったりすることがあります。
たとえば…
- 体育の時間が苦痛で、学校に行きたくなくなる
- 友だちと遊ぶときに動きが遅れて、仲間に入れない
- 自分を「できない子」と思い込み、自信をなくす
こうした状態が続くと、やがて不登校やうつ状態などの二次的な問題に発展する可能性もあるのです。
大切なのは、「理解」と「支援」
DCDの子どもをサポートするために、まず必要なのは、周囲の大人がDCDという特性を知ることです。
「なんでこんなこともできないの?」
「集中力がないからだ」「やる気が足りない」
そんなふうに責める前に、「この子の中で何が起きているのか?」を考えてみてほしいのです。
DCDの支援では、以下のような工夫が効果的とされています。
- 体育や行事の前に、個別にやり方を予習しておく
- 苦手な動作はスモールステップで練習する
- 運筆を助ける補助具(鉛筆グリップ、滑り止めつき定規など)を活用する
- 筆圧や姿勢の安定を助けるマットや下敷きを使う
- 子どもが「できるようになりたいこと」を丁寧に聞いて、一緒に取り組む
さらに、子どもが「できた!」「がんばれた!」と感じられるような体験を積み重ねることが、自己肯定感を育てる大きなカギになります。
苦手も「その子らしさ」の一部
DCDの子どもたちは、「できないこと」に意識が向けられやすいけれど、
よく観察してみると、得意なことや豊かな感性、想像力をもっている子がたくさんいます。
「できないこと」はあっても、「ダメな子」なんかじゃない。
その子に合ったやり方を見つけて、そっと背中を押してくれる大人がいれば、
子どもはちゃんと、自分の力で前に進んでいけます。
最後に──
私は、自分の子ども時代を振り返って、
「運動が苦手でも、私は私でよかった」と今では思えます。
でも、あのとき「わかってくれる誰か」がそばにいてくれたら、
もっと早く、自分に自信を持てたかもしれない。
だから今、DCDという特性がもっと広く知られて、
同じように苦しんでいる子どもや親御さんが少しでも楽になれたら…
そんな思いで、この記事を書きました。
「もしかしてうちの子も?」と感じたら、どうか責めたり急がせたりせず、
子どもと一緒に、ゆっくりと前に進んでいってほしいと思います。