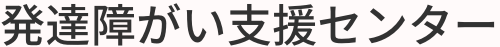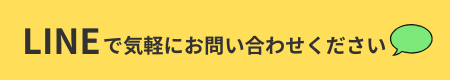こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
発達障害のある方の中には、
「なかなか眠れない」
「夜中に何度も起きてしまう」
「朝がつらい」…そんな“睡眠の悩み”を抱えている人が少なくありません。
今回は、なぜ発達障害のある人は眠りにくいのか?
そして、より良い睡眠をとるためにできる工夫について、わかりやすくお伝えします。
なぜ眠りづらいの?
発達障害のある方が睡眠で困りごとを感じやすい理由は、いくつかあります。
① 脳の働きの違い
自閉スペクトラム症(ASD)やADHDのある人は、脳の覚醒状態を調整するのが難しいといわれています。
そのため、夜になっても頭が冴えていたり、眠気を感じにくかったりすることがあります。
② メラトニンの分泌が少ない
眠気を誘うホルモン「メラトニン」が十分に分泌されにくい体質の人もいます。
これはASDの人に特に多くみられます。
③ 感覚が敏感すぎる
音や光、布団の感触などが気になって眠れないこともあります。
「ちょっとした物音で目が覚める」「シーツのしわが気になる」など、感覚過敏が原因のことも。
睡眠をよくするための7つの工夫
眠りにくさを少しでもラクにするために、今日からできる対策をご紹介します。
① 決まった時間に寝て、決まった時間に起きる
毎日の睡眠リズムを整えることで、体が「そろそろ寝る時間だな」と自然に感じるようになります。
② 夜のスマホ・パソコンは控えめに
スマホやゲームのブルーライトは、眠気を妨げる原因に。
できれば寝る1時間前には画面をオフにしましょう。
③ 寝る前にリラックスタイムを
ぬるめのお風呂、好きな音楽、ストレッチ、アロマなどで、心と体をゆるめてから布団に入りましょう。
④ 寝室を自分好みに整える
光を遮るカーテン、静かな空間、肌触りのよいパジャマなど、自分にとって心地よい空間を作ることが大切です。
⑤ 朝の光を浴びる
起きたらすぐにカーテンを開けて、太陽の光を浴びましょう。
これが体内時計のリセットになります。
⑥ 昼寝は15~30分までに
日中の仮眠は短時間ならOK。でも、長すぎると夜眠れなくなるので注意。
⑦ メラトニンや漢方などを医師と相談して使う
どうしても眠れないときは、メラトニンのサプリや漢方薬などを専門家と相談のうえで使うのもひとつの方法です。
睡眠は「心と体のメンテナンス時間」
眠ることは、ただ休むだけじゃありません。
その日の疲れを回復し、気持ちを整えるための大切な時間です。
睡眠がとれるようになると、気分も落ち着きやすくなり、集中力も少しずつ上がっていきます。
完璧に眠れなくても大丈夫。
「少しでも眠れるようになるには、どうしたらいいかな?」とやさしく自分に問いかけて、できることから取り入れてみましょう。
眠れないのは、あなただけじゃない
睡眠の悩みを抱えているのは、あなただけではありません。
同じように悩みながら、少しずつ眠りやすい方法を見つけている人がたくさんいます。
大切なのは、「眠れない自分はダメ」と責めないこと。
まずは、自分に合った方法を探してみようと、前向きな一歩を踏み出してみましょう。
あなたがぐっすり眠れて、気持ちよく朝を迎えられる日が来ることを、心から願っています。